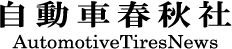住友ゴム工業は6月21日、理化学研究所(理研)が所有する放射光施設の見学会を開催した。同社研究開発本部分析センターの岸本浩通センター長は住友ゴムの材料開発に関する発表を行い、大型放射光施設「SPring-8」(スプリングエイト)やX線自由電子レーザーの「SACLA」(サクラ)をはじめとする先端研究施設の活用事例を紹介。また、施設の進化や「Society(ソサエティー)5.0」の実現に伴う環境変化が、未来の新材料開発につながる可能性があると展望を示した。
タイヤのゴムは天然ゴムや合成ゴム、シリカといった10種類以上の材料が混ざり合っており、ゴム内部では、これらの材料がナノスケールからマイクロスケールまで階層構造を形成している。この階層構造の解明

こそがタイヤ性能向上のヒントになる。ただ、仮にタイヤが地球サイズであればナノレベルは1円玉サイズとなってしまうように、ゴムの材料構造の解析は容易ではない。そのため、巨大な顕微鏡として働く「SPring-8」のような先端研究施設の活用が必要になる。
岸本氏は「多くの先端研究施設を特徴に合わせて使い分けし、常に活用し続けているからこそ、当社では先端のゴム材料技術が作り出せている」と説明する。
これまで住友ゴムでは、「SPring-8」や「SACLA」をはじめ、大強度陽子加速器施設「J-PARC」(ジェイパーク)、中型放射光施設「SAGA(サガ)-LS」といった先端研究施設と、スーパーコンピューター「地球シミュレータ」および「京」の連携活用が進められてきた。
2011年には、「SPring-8」と「地球シミュレータ」の活用によって材料開発促進技術「4D NANO DESIGN」(フォーディー・ナノ・デザイン)を確立。これによって、“シリカを配合すると、何故ゴムの強度やグリップ性能が向上するのか”といった、それまで明らかにされていなかったメカニズムを研究し、解明することが可能になった。
シリカのケースでは「SPring-8」を活用し、ゴムを変形させながらX線を照射する実験を行い、ゴム内部のシリカの構造変化などを示すX線散乱像を取得。その上で「地球シミュレータ」による解析を実施し、ゴムを引っ張った時にシリカの配置がどのように変化し、ゴムのグリップ、燃費に影響を与えているのかを可視化することに成功した。

2015年には、新材料開発技術の「ADVANCED 4D NANO DESIGN」(アドバンスド・フォーディー・ナノ・デザイン)が完成した。同技術を採用した「エナセーブNEXTⅡ(ネクストツー)」には、「J-PARC」の実験で得られたシリカとポリマーの結合剤に関する新知見や、「京」を用いたゴムの破壊のシミュレーションが活用された。
2019年、住友ゴムはAI技術「Tyre Leap AI Analysis」(タイヤ・リープ・エーアイ・アナリシス)を確立した。使用後のタイヤ画像を同AI技術に入力すると、新品との違いを判定し、ゴム内部の変化をフィードバックすることなどができる。
同年発売の「エナセーブNEXTⅢ(ネクストスリー)」は、このAI技術と、先端研究施設での解析およびシミュレーション技術を活用した。具体的には、AI技術によって判断したゴムの表面や内部構造の変化について「SACLA」や「SAGA-LS」を用いて解析。また、シミュレーション技術も応用することで、「水素添加ポリマー」の開発につなげ、同ポリマーを採用した「エナセーブNEXTⅢ」では性能変化の抑制を実現した。

未来のタイヤゴム材料開発には、Society5・0の実現に向けた環境変化が影響を与える見通しだ。例えば、タイヤでは空気圧や摩耗状態をセンシングすることが可能になってきているが、クラウド上でこれらの情報のビッグデータ解析を行うことで、メンテナンスフリーなサブスクリプション事業への転換が実現するなど、様々な新サービスや新製品の展開が進んでいくと考えられる。
こうしたタイヤを取り巻く環境の進展を通じ、「『Tyre Leap AI Analysis』でタイヤの使用前と使用後だけでなく、その途中の“使われ方”まで考えた材料開発を実現する可能性が生まれる」(岸本氏)という。

また、先端研究施設が進化することで取得可能なデータの量も膨大になってきており、同社では、新材料開発につながるビッグデータ解析技術の検討も始めた。さらに、今年活用を開始したスパコン「富岳」にも期待がかかる。
岸本氏は「『京』よりも広いスケールや、走行中の化学変化を捉えるシミュレーションによって新材料開発を促進させていきたい」と意気込みを話した。
「SPring-8」は理研が所有する放射光施設で、1997年に供用開始した。同施設では、電子銃から打ち出した電子が1周約1.5kmの円状の加速器などを通った後、磁石を利用して電子からエネルギーが取り出される。このエネルギーこそが放射光で、実験では放射光の中でも主にX線を活用。ゴムをはじめ様々な試料にX線を照射することにより、検出器でX線散乱像など多様なデータを取得することが可能だ。
「SACLA」も放射光施設で、直線の加速器を通過した電子からX線レーザーを生成し、これを試料に当てることでデータが得られる。岸本氏によると、「化学反応のような瞬間を捉える際に利用する」という。同施設は長さが約700mで、供用開始は2012年から。
理研の放射光科学研究センターの石川哲也センター長は、今後、産業界の施設利用を支援するシステムなどを充実することで、「諸外国に比べて一段、二段と画期的なものを生み出していきたい」と抱負を述べていた。