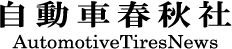JATMA(日本自動車タイヤ協会)は、国内における2024年(1月—12月)の廃タイヤ(使用済みタイヤ)の発生量と有効利用量をまとめた。タイヤ取替時、廃車時の発生量は合計8900万本で、前年比100万本減。有効利用量は69万2千トン。「有効利用量」/「有効利用量+非有効利用最終処分量」×100で算出した有効利用率は99.6%で、前年実績に比べて0.4ポイント増加した。
〈表1〉のように、24年の廃タイヤの発生量について、ルート別に分析すると「タイヤ取替時」の発生量は7800万本。市販用タイヤの販売が前年並みで、廃タイヤの発生量も前年と同程度となった。

「廃車時」は1100万本。廃車台数が前年比4.5%減の260万8千台と、この10年間で最も低い水準にとどまったことを受け、廃タイヤの発生量も前年から100万本減少した。
有効利用量は〈表2〉の通りで、70万トン台を割った。増加傾向が続いていた「製紙工場」での燃料利用が一転し6万3千トンも急減。「化学工場」「セメント工場」なども減少傾向のまま推移した。

このようなサーマルリサイクルに対し、資源循環社会をめざす取り組みの一環としてケミカルリサイクルへの関心が高まっている。「熱分解施設」での利用は前年より2千トン増加。マテリアルリサイクルである「再生ゴム・ゴム粉」とともに増加トレンドを示す。今後の動きが注視される。
なお、前回の調査から、更生タイヤ(リトレッドタイヤ)は除外されている。更生タイヤは使用されている限り廃タイヤにならず、発生量・有効利用量に影響がないことがその理由。
一方で、国内の熱利用先が海外から廃タイヤの切断品・破砕品を有価購入する状況が続いている。24年の年間輸入量は、集計開始以来過去最高を記録した前年実績を更新し、約3万トン増の約17万240トンだった。
不法投棄残存量は増加
廃タイヤの不法投棄残存量は25年2月の調査時点で79件、2万3880トン。前年の調査時と比較し、件数で4件増加した。内訳は撤去完了2件、新規判明6件。重量は115トン増加。