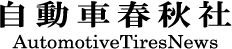「激戦区のクロスオーバーSUV、その足元」

モータージャーナリストの瀬在仁志さんが「10数年ぶりに復活したロータリーエンジン搭載車です」と示すクルマ。それがマツダ MX−30 Rotary(ロータリー)−EVだ。ロータリーエンジンはマツダが世界で唯一、実用化に成功し市販車モデルに搭載した。それもRX−8が12年に生産終了したことで、マツダのアイデンティティが途絶えたようにみえた。しかし今回、人気のSUVの分野でPHEVとして復活した。
コスモスポーツ、ルーチェ、サバンナ、カペラ、ファミリア……。70年代に運転免許を取った世代は、ロータリーエンジンと言えばこれらの車名がすらすらと挙がるのではないか。車名のあとに「ロータリークーペ」とつづいて。
03年に発売されたRX−8が市販車として最後のロータリーエンジン搭載車。その生産が終了されてから10数年経ち、MX−30 Rotary−EVでロータリーエンジンの搭載が電撃的(EVだけに言い得て妙)に復活した。
そもそもロータリーエンジンとはどんなものなのか。瀬在さんに解説してもらうと次のようだ。

内燃機関は吸気・圧縮・膨張(燃焼)・排気という四つの行程が繰り返される。一般的なエンジン(レシプロエンジン)は、一つのシリンダー(気筒)の内部でピストンの往復運動が回転運動に変換され、前述の4サイクルが順番に行われる。
対して、ロータリーエンジンはローターハウジング(レシプロエンジンでのシリンダーの役目)の内部で三角おむすび型のローターがハウジングの壁面に沿って回転することで4サイクルが行われる。ロータリーの回転で点火・爆発という燃焼行程が複数、同時進行するというのが前者と大きく異なるところだ。
このため「少ない排気量でも高出力で大きなパワーを発揮することができる」「小型で軽量」という特性を持つ。クルマの低重心化が可能で、エンジンルームにコンパクトに配置できることから、スポーツ系のクルマと相性が良いという。
一方で「燃焼時の密閉を保つためのシール部品や、回転によって生じる摩耗にいかに対応するかなど、技術的課題も多かった」と、瀬在さんは指摘する。このため実用化をめざす欧州車メーカーは軒並み開発から撤退した。だがマツダはただ1社、それに取り組み解決しロータリーエンジン車を供給しつづけていた。

ル・マン24時間レースで日本車メーカーとして初めて総合優勝を果たしたのがロータリーエンジン搭載の787B。また低く構えたスタイルに、ロータリー独特のエンジンサウンドを奏でたRX−7は、全日本ツーリングカー選手権など数々のモータースポーツシーンで勝利を獲得。いまも多くのファンから高い支持を得ている。レースゲームや映画でシンボリックなスポーツカーとして登場するのはその証左だ。
そのようなロータリーエンジン車の系譜に名を刻むMX−30 Rotary−EV。ただし「パワートレインとしての復活ではありません。発電するための発電機としてロータリーエンジンが採用されました」と、瀬在さんは解説する。
今回試乗したグレードはNatural Monotone(ナチュラルモノトーン)で、駆動方式は2WD(FF)。e−SKYACTIVE R−EV、水冷1ローターのエンジンを搭載する。

カタログデータによると、エンジン最高出力は53kW(72PS)/4500rpm、エンジン最大トルクは112N・m/4500rpm。モーター最高出力は125kW(170PS)/9000rpm、モーター最大トルクは260N・m/0−4481rpm。
サイズは全長4395ミリ×全幅1795ミリ×全高1595ミリ。ホイールベース2655ミリ。車両重量1780キロ。ハイブリッド燃費はWLTCモード走行燃料消費率15.4km/ℓ。EV走行換算距離107km。
MX−30 Rotary−EVは5人乗りのクロスオーバーSUV。競合する車種が非常に多い。それだけにデザインや機能面で差別化が図られている。その代表が後部座席側のドア。外見ではピラーレスの2ドアなのだが、後部座席への乗り降りに際し、「フリースタイルドア」と呼ばれる観音開きのドアを内側から開ける。2ドアの高いスタイリッシュ性を維持しながら、乗降をしやすくするサポート機能だ。
ただ、これが慣れるまで結構やっかいだった。SUVを試乗する際に後部座席を使い車内の居住性を確認するのだが、今回このフリースタイルドアに手こずった。これは前部ドアを先に開けてからでないと開閉できない。閉めるときもフリースタイルドアが先。2ドア車だから理屈としてはわかるのだが、そこにドアがあれば習慣で通常の後部ドアと勘違いしてしまい、ついうっかりと無駄な動きを起こしてしまう。
強風時、駐車場で隣のクルマへのドアパンチに配慮する必要があるシーン。観音開きの場合、ドライバーがひとりで前部ドアとフリースタイルドアを同時に半開きを維持しながら、後部座席の利用者(たとえば幼児やお年寄り)の乗降をエスコートするのはかなりむずかしい。
マツダはロータリーエンジンやディーゼルエンジンについて、深いこだわりを持つメーカーだ。そのクルマづくりへのこだわりが独自性としてファンの心情を鷲づかみして離さない。ただ、フリースタイルドアのような、一般的な使いかた・使われかたとフィットしないものがほかにもあるようだ。それがこのクルマの普遍化を妨げていると、指摘する声が聞かれる。
クロスオーバーSUVらしく、MX−30 Rotary−EVは軽快でスポーティな走りが身上。ドライビングレンジの居住性も高い。その性能を支えるのがタイヤだ。
このクルマに装着されていたのはブリヂストンのTURANZA(トランザ) T005A。サイズはフロント・リアともに215/55R18 95H。転がり抵抗を低減し優れた燃費を実現しながらドライ&ウェット性能、コンフォート性能を両立する。
この装着タイヤは商品設計基盤技術、ENLITEN(エンライトン)が採用される前のもの。クロスオーバーSUV装着タイヤに求められるのはトータルバランス。それにENLITENが搭載されることで、時代の潮流であるPHEVを含む、EVの走りがどう変わっていくのだろうか。
=瀬在仁志(せざい ひとし)さんのプロフィール=

モータージャーナリスト。日本自動車ジャーナリスト協会(AJAJ)会員で、日本カー・オブ・ザ・イヤー選考委員のメンバー。レースドライバーを目指し学生時代からモータースポーツ活動に打ち込む。スーパー耐久ではランサーエボリューションⅧで優勝経験を持つ。国内レースシーンだけでなく、海外での活動も豊富。海外メーカー車のテストドライブ経験は数知れない。レース実戦に裏打ちされたドライビングテクニックと深い知見によるインプレッションに定評がある。